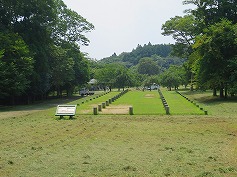| 仙台城 100名城(最終訪城日:平成25年8月8日) |
|
|||||
 復元 大手隅櫓 |
|
|||||
| 仙台城は初め千体城、後に千代城と称し、鎌倉時代末から室町時代の中頃にかけて島津氏が陸奥守として居城したといい、室町時代末には国分氏が一時居城したと伝えられています。伊達政宗が自然林と断崖と川に囲まれた天然の要害青葉山に築城を開始したのは関ヶ原合戦直後、慶長5年(1600)のことである。この時、地名は千代から仙台に改められました。二代忠宗は寛永15年(1638)二の丸を造営、その後も整備拡充と被災を繰り返しながら幕末に至りました。 『現地案内看板より本文抜粋』 |